【はじめに】
介護の仕事をしていて、ふと思うことがある。
利用者さんやご家族からの「ありがとう」や「笑顔」は、確かにやり甲斐を感じる瞬間だ。
けれど、それだけでは長く続けていくことは難しい。
プロとして私たちが目指しているのは、「感謝されること」ではなく「信頼されること」。
そのうえで感じるやり甲斐には、もう少し深い構造があると感じている。
【やり甲斐の“三層構造”】
やり甲斐には、実は3つの層がある。
- 利用者・家族からのやり甲斐
感謝や笑顔という“心の報酬”。 - 会社からのやり甲斐
評価と報酬という“制度の報酬”。 - 自分自身からのやり甲斐
成長や達成感という“内なる報酬”。
この3つがそろったとき、仕事は「志をもって行う志事(しごと)」になる。
しかし、どれか一つでも欠けてしまうと、それは「心が枯れていく死事(しごと)」に変わってしまう。
【心が枯れないために】
介護の仕事は、感情を扱う繊細な仕事だ。
どんなに優しくても、どんなに努力しても、報われないと感じる瞬間はある。
それでも前を向ける人の多くは、自分の中に“成長の実感”を持っている。
「昨日より今日の自分の方が、少しだけうまく関われた」
「利用者さんの気持ちを、ほんの少し深く理解できた」
そんな小さな変化の積み重ねが、最も強いモチベーションになる。
【おわりに──やり甲斐を“育てる”ということ】
やり甲斐は“もらうもの”ではなく、“育てるもの”。
感謝・評価・成長という3つの報酬を、自分の中でバランスよく育てていく。
その積み重ねが、やがて「志事」と呼べる仕事に変わっていくのだと思う。
今日も現場で奮闘するすべての介護職の皆さんへ。
どうか、自分の「やり甲斐」を誰かに委ねず、自らの手で育てていってほしい。
それが、ケア壱的“志事”の哲学です。

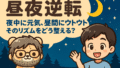

コメント