「どうすればスタッフが本気になってくれるのか?」
介護リーダーであれば、一度はぶつかるこの壁。
指示は出している。伝えている。なのに、現場はどこか“他人事”の空気。
私もその空気感に悩まされていた一人です。
でも、ある視点を持つことで、スタッフが自ら“本気で動き出す”場面が増えてきました。
今回は、現場で実感した「本気を引き出すリーダーの視点」についてお話しします。
1. なぜスタッフは「やらされ感」に陥るのか?
- 業務に目的を感じていない
- 成果が“自分ごと”になっていない
人は「意味がわからないこと」には本気になれません。
スタッフにとって“やる理由”があいまいなままだと、どうしても「やらされている」感覚が生まれてしまいます。
また、成果が“誰かのため”ではなく、“自分ごと”として実感できていないと、モチベーションが続きません。
2. 本気が引き出される瞬間に共通するもの
- “意味づけ”と“共感”
- 小さな成果の積み重ね
- 仲間からのフィードバック
現場で観察していて感じたのは、「自分の行動が誰かの役に立っている」と気づいた瞬間、スタッフの目の色が変わることです。
意味づけを丁寧に行い、共感を得られる環境づくりを意識することが、本気を引き出す土台になります。
3. リーダーにできる関わり方
- 「問いかけ」の技術
- 失敗をチャンスに変える視点
- 信頼貯金の残高確認
指示よりも「問いかけ」が人を動かすと感じています。
「どう思う?」「なぜそうしたの?」といった問いかけが、スタッフの内面を刺激します。
また、失敗を否定するのではなく、「どうすれば次はうまくいく?」と視点を変えることで、前向きな姿勢を育むことができます。
4. 現場で実践した2つのアプローチ
- 朝礼で共有する“意味”の時間
- 感謝を記録する「リフレクションノート」
朝礼の数分間を使って、「今日の業務の意味」や「誰のためにやるのか」を共有するだけで、現場の雰囲気が変わりました。
また、終業後に“感謝したこと”を記録するリフレクションノートは、チーム内の信頼を深め、本気の連鎖を生みました。
5. まとめ:本気は“作らせる”ものではなく、“芽吹かせる”もの
本気は強制できるものではなく、「自ら湧き出る」もの。
リーダーができるのは、土を耕し、水を与え、芽が出るのを信じて待つことです。
その姿勢が、スタッフの心に届き、やがて“本気”という芽が育っていくのです。
👉 記事一覧はこちら


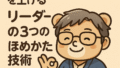
コメント