かつては「根性論」や「気合い」で育成されるのが当たり前でした。
しかし、現代の介護現場では“考え、行動するスタッフ”が求められています。
そこで注目したいのが「コーチング」。
この記事では、スタッフが自主的に動けるようになるために、 介護リーダーが押さえておきたい「コーチングの考え方と使い方」を解説します。
コーチングとは?
コーチングとは、問いかけを通して“気づき”を促す関わり方です。
- 指示や命令ではなく、「どう思う?」「なぜそう考えたの?」という質問で、
- 相手が自分自身の答えを導き出す機会を作ります。
つまり、“自ら考える力”を育てるアプローチです。
ティーチングとの違い
| ティーチング(教える) | コーチング(引き出す) |
|---|---|
| 知識・技術を伝える | 気づき・判断力を育てる |
| 一方的な情報伝達 | 双方向の対話 |
| 初学者への指導に適する | 基礎があるスタッフの育成に適する |
コーチングが必要な“育成段階”
スタッフの成長には段階があります。
- ティーチング(基礎知識の習得)
- コーチング(気づき・判断力の促進)
- 任せる(自立と信頼)
コーチングは、**「ある程度の知識・技術が身についた段階」**で行うのが効果的です。
「まだ早い」と感じる場面では、無理にコーチングせず、 ティーチングに戻ることも必要です。
コーチングのメリット
- 自分で考える力が育つ
- 個性や価値観を活かせる
- 判断力が身につく
- リーダーも新たな視点を得られる
ときには、リーダー自身が思いつかないようなアイデアが出ることもあり、 学び合う関係が築けます。
コーチングの注意点・デメリット
- 時間がかかる(対話の積み重ねが必要)
- 相手の準備レベル(エビデンス)に左右される
- すぐに成果が見えにくい
「まだ教えた方が早い」と感じても、育成の視点で“待つこと”もリーダーの仕事です。
ティーチング・コーチング・任せる
どれか一つに偏るのではなく、 **「段階を踏んでバランスよく使い分ける」**ことが人材育成の鍵です。
❌ ずっと教え続ける(=依存が育つ)
❌ 早すぎるコーチング(=混乱や放置感)
👉 状況と相手に応じて切り替える柔軟さが求められます。
コーチングの応用:家庭・子育てにも
実はコーチングは、仕事だけでなく子育てや人間関係にも応用できます。
私自身も、「人材育成=子育て」だと気づいたとき、 家族との関係性が大きく変わりました。
まとめ:コーチングは“育てて任せる”ための通過点
コーチングは、ティーチングの次にくる“育成の要”です。
スタッフの力を信じて問いかけ、 自分で答えを出し、成長する機会を提供することで、 「任せられるスタッフ」が育ちます。
その第一歩として、今日から「問いかけてみる」ことから始めてみましょう。


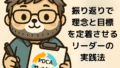
コメント