はじめに:支援者にも守られる権利がある
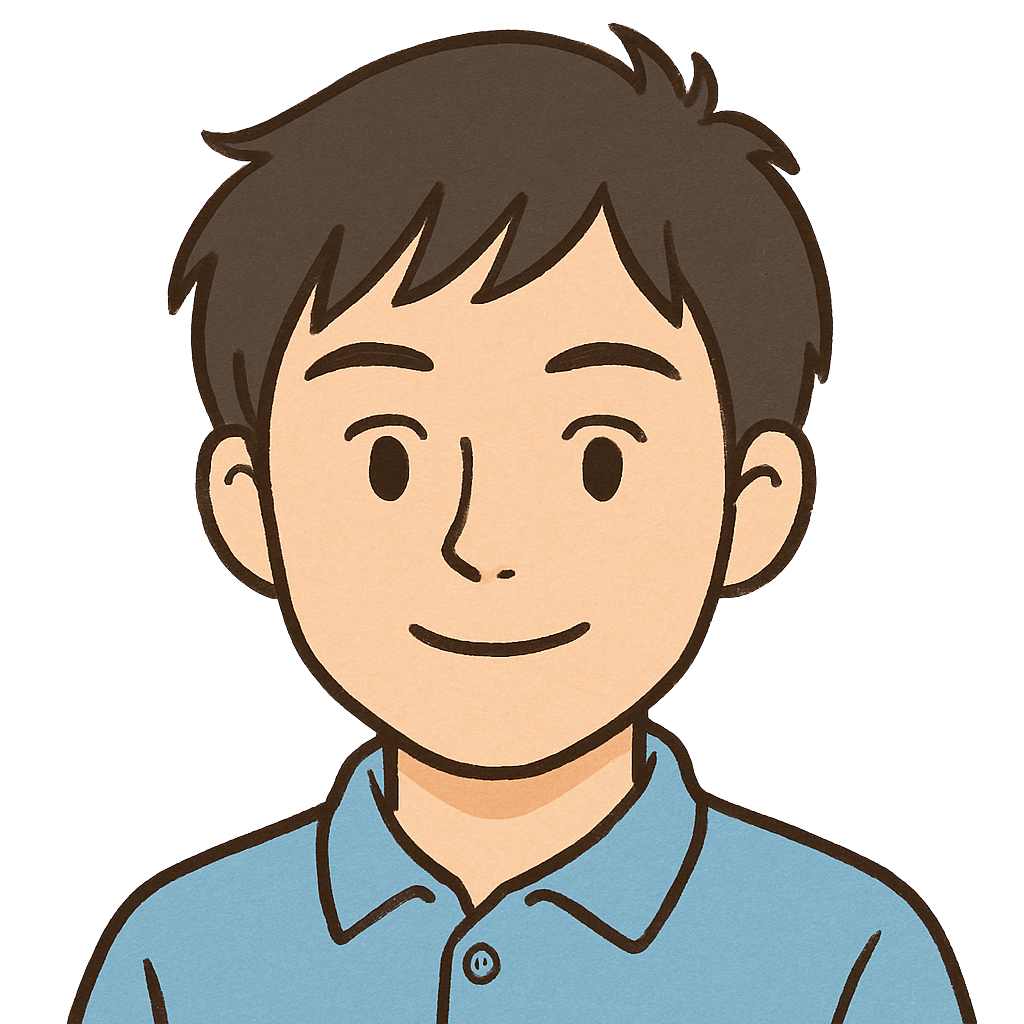
前回、利用者の権利はよくわかりました。でも…僕たち介護職にも守られる権利ってあるんですか?

もちろんあるよ。実は、介護職の人権が軽視されてきた歴史もあるんだ。今日は“支援者の権利”と“コンプライアンス”の使い方を一緒に考えていこう。
利用者から介護職へのハラスメントとは?
介護現場では、「我慢」が美徳とされがちです。しかし、以下のようなケースは明確にハラスメントに該当します。
| ハラスメントの種類 | 具体例 |
| 暴力 | つねる、叩く、物を投げる |
| 暴言 | 「給料泥棒」「バカ」「殺すぞ」など |
| セクハラ | 体に触れる、性的な言動を繰り返す |

「“利用者だから仕方ない”と片付けるのはもうやめよう。これは“介護職の人権”の話なんだ。
🔹余談:見えにくい“男性へのセクハラ”
一般的に、セクシャルハラスメントの被害は女性スタッフに多く報告されますが、実際には男性職員に対しても同じくらいの割合で発生していると言われています。ただし、男性スタッフは「体力があるから耐えられる」「冗談として流せる」と周囲に見なされがちで、声に出しにくい雰囲気の中で我慢してしまうことが多いのが実情です。また、実際に体力差があるので、「触る」などの行動を避けることができるため、”報告しない”ことも多いのも事実です。
コンプライアンスは“職員を守る道具”
「コンプライアンス」とは、単なる“法令順守”ではなく、働く人を守るための行動規範でもあります。
🔸コンプライアンスの活用例
| 行動 | 対応 |
| ハラスメントの記録 | 日誌・報告書・ヒヤリハットへの記録 |
| 上司や第三者への相談 | 内部相談窓口・包括支援センター・労働局など |
| 組織としての対処 | 利用者への対応変更、担当替え、契約見直しなど |

制度は守らされるものじゃない。使いこなすことで、自分や仲間を守る“盾”にも“道具”にもなるんだよ。
実際にあった事例:対応の差が命運を分ける
【事例1】セクハラ発言を繰り返す利用者への対応
→ 記録がなく事実確認(証拠)ができず対応が遅れる、職員個人のストレスだけが蓄積 → 退職へ
→ 記録(証拠)と相談を重ね、上司が担当替え・包括と連携 → 職員は継続勤務

「“記録”と“報告”は、自分を守る正当な手段。黙って耐えるのが正解じゃない。
まとめ:介護職の誇りを守るために
- 利用者の権利と同様に、介護職にも守られるべき権利がある
- ハラスメントや暴力に対して、“個人で抱え込まない”仕組み作りが大切
- コンプライアンスは“盾”でもあり“道具”として活用できる

介護の仕事は、人の人生を支える仕事。だからこそ、支える側のあなた自身も、ちゃんと守られていいんだよ。
✉️次回予告:記録は“守る力”になる
次回のテーマは「記録」。
「利用者のための記録」と「支援者を守る記録」は、同じ“書く行為”でも意味と重みが違います。
現場でよくある「忙しくて書けない」「どう書けばいいかわからない」という悩みも含めて、
記録が“自分と仲間を守る力”になるという視点で、ケア壱とユウキが一緒に考えていきます。

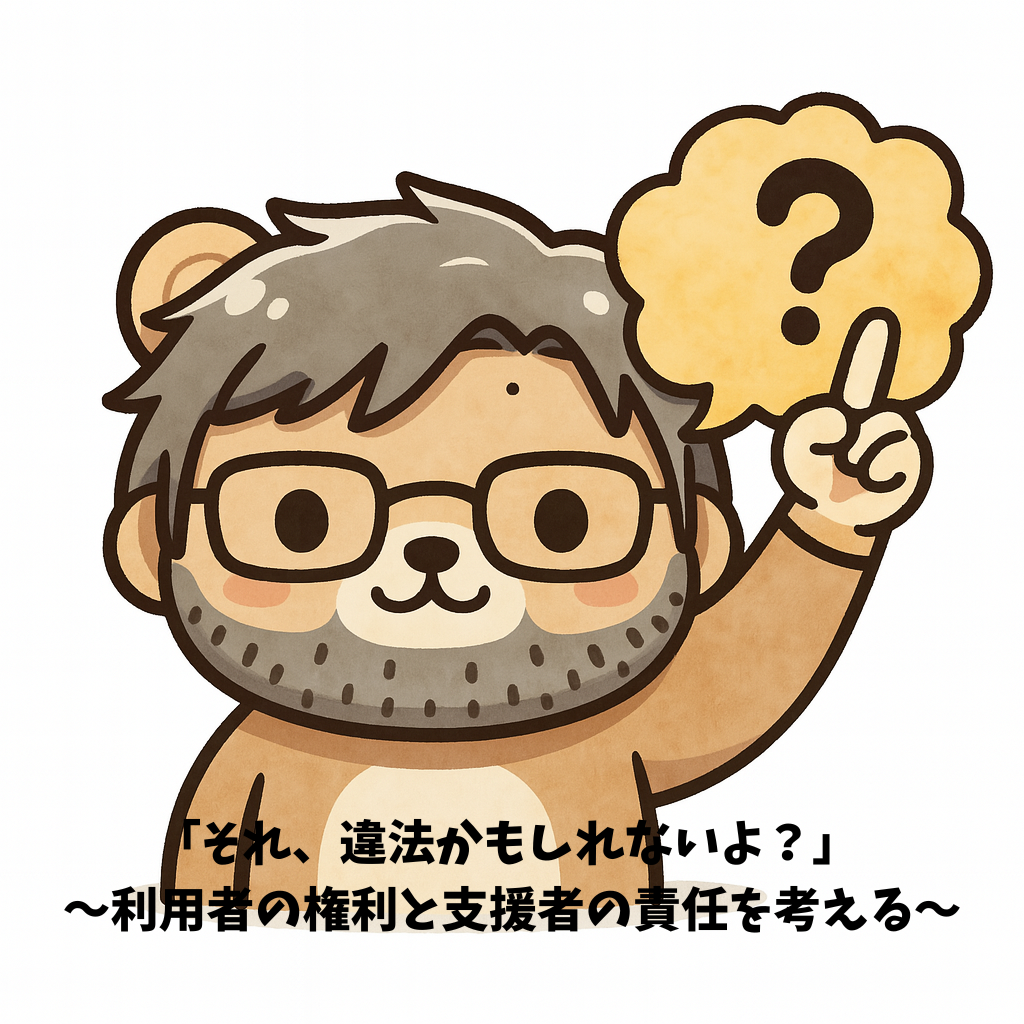
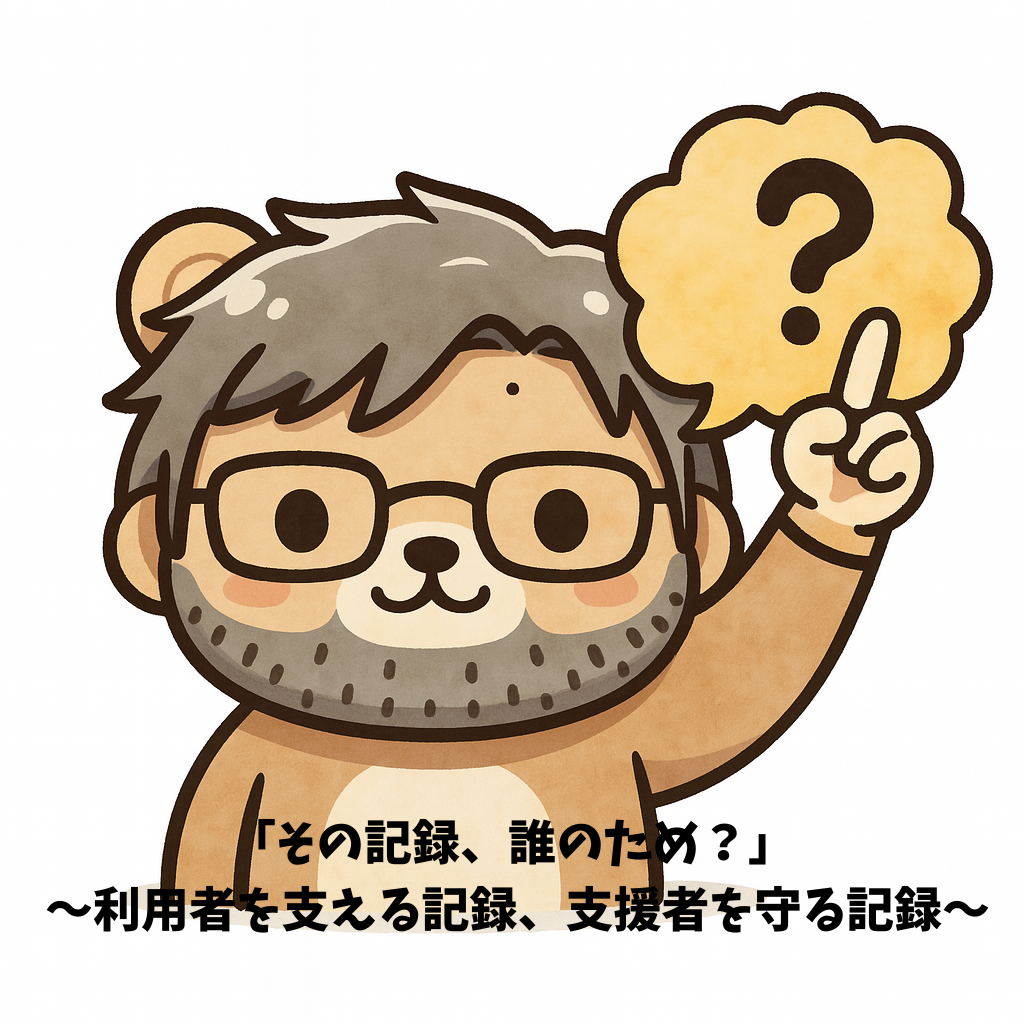
コメント