はじめに:ある夜勤明けの会話から
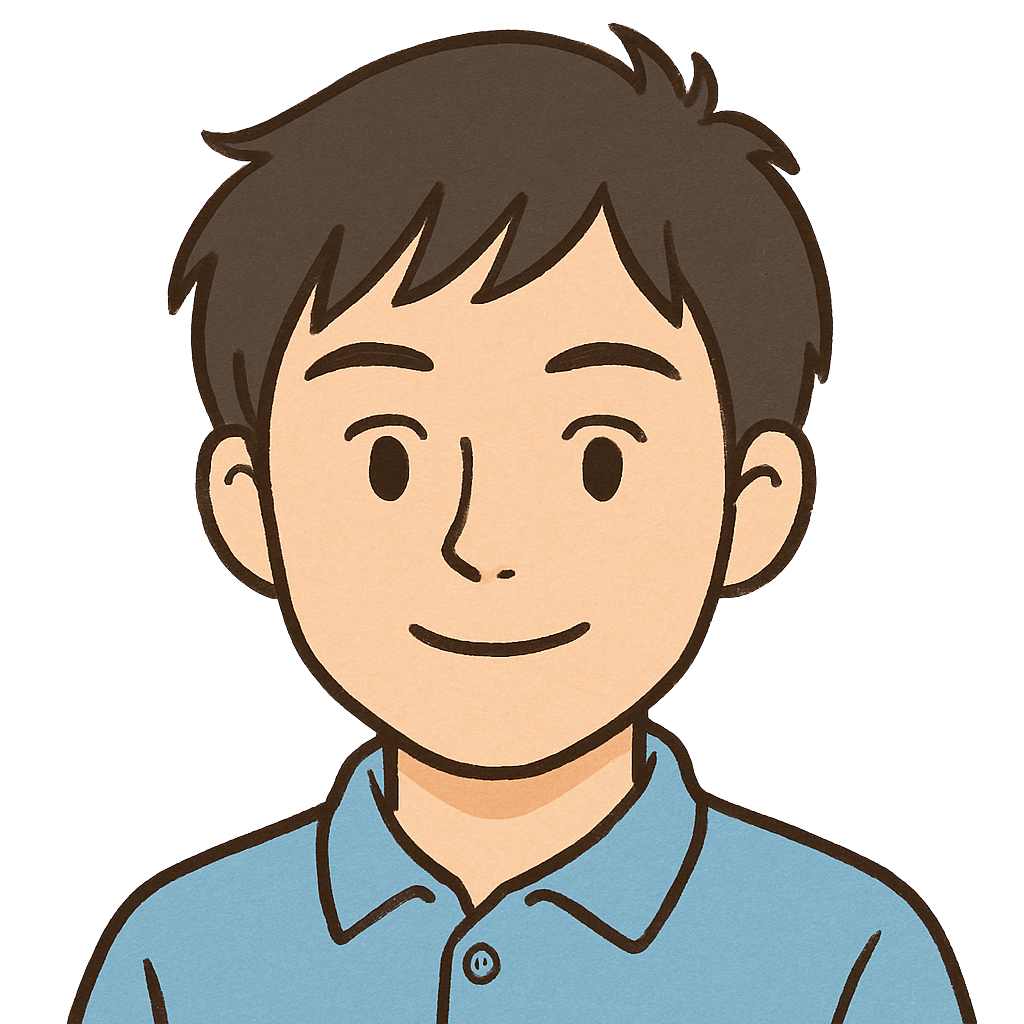
ケア壱さん、昨日の夜勤で、○○さんに急に怒鳴られて…しかも、腕つかまれてすごく怖かったんですけど…。これって我慢しなきゃいけないんですか?

うん、その話、すごく大事だね。実は“利用者の権利”って言葉の裏には、“支援者としての責任”があるんだ。今日はそこを一緒に整理してみようか。
利用者の権利とは何か?
介護現場でよく耳にする「利用者の人権」や「尊厳の保持」。これは単なるスローガンではなく、介護保険法や高齢者虐待防止法などに明記された法的に守られるべき権利です。
🔹利用者の主な権利
| 権利の種類 | 内容 |
|---|---|
| 自己決定権 | 自分の生活・ケアを自分で選ぶ権利 |
| 人格の尊重 | 侮辱・差別・威圧を受けない権利 |
| 安全の権利 | 危険や不衛生から守られる権利 |
| プライバシー権 | 個人情報や生活空間が守られる |

例えば、オムツ交換のときに声かけなしでめくったら、それって“プライバシー権の侵害”にあたるよ。
こうした権利は、たとえ認知症や障害があっても失われるものではありません。
支援者の力と責任
支援する側である介護職は、利用者に対して圧倒的に優位な立場にあります。
- 力や身体機能の違い
- 専門知識と判断力の差
- 支援内容を“決める”側にいる
この非対称性があるからこそ、「支援者の行動は慎重でなければならない」とされます。

介護職が怒鳴ったら“虐待”になるけど、利用者が怒鳴ったら“ご機嫌斜めかな”ってなること、あるでしょ?
このバランスの違いを意識することが、支援者としての責任の第一歩です。
虐待との境界線
虐待は“わざと”でなくても成立します。以下のような例もすべて虐待にあたる可能性があります。
🔸虐待の具体例(表)
| 種類 | 例 |
| 身体的虐待 | 強く腕を引っ張る、叩く |
| 心理的虐待 | 無視する、大声で怒鳴る |
| 性的虐待 | 着替え中に必要以上に見る・触れる |
| 経済的虐待 | 金銭管理を本人の意向なく行う |
| 介護放棄 | 必要な支援を故意に行わない |

「“やってしまった”で済まされる話じゃない。大切なのは、“していない”と言える記録と行動を残すこと。
まとめ:まずは「守る側としての自覚」から
介護職がまず理解すべきなのは、
- 利用者の権利は法律で守られていること
- 介護職は支援する力を持つがゆえに慎重さが求められること
- 虐待は“意図がない”場合でも成立すること

利用者の権利を守るっていうのは、正義感とか優しさだけじゃなくて、“法律を守る”っていうプロ意識でもあるんだよ。
✉️次回予告:「それ、違法かもしれないよ?」 〜利用者の権利と支援者の責任を考える〜【後編】
利用者の権利を守ることは、介護職としての基本です。
けれど、その“守る側”である私たちにも、時に傷つく場面や理不尽な扱いを受けることがあります。
次回は「介護職の権利」をテーマに、利用者からのハラスメントや暴力へのケア壱は名探偵??― 認知症ケアと推理脳シリーズ ―対応、そして「“コンプライアンスを使って自分を守る”という視点」をケア壱とユウキが深掘りしていきます。
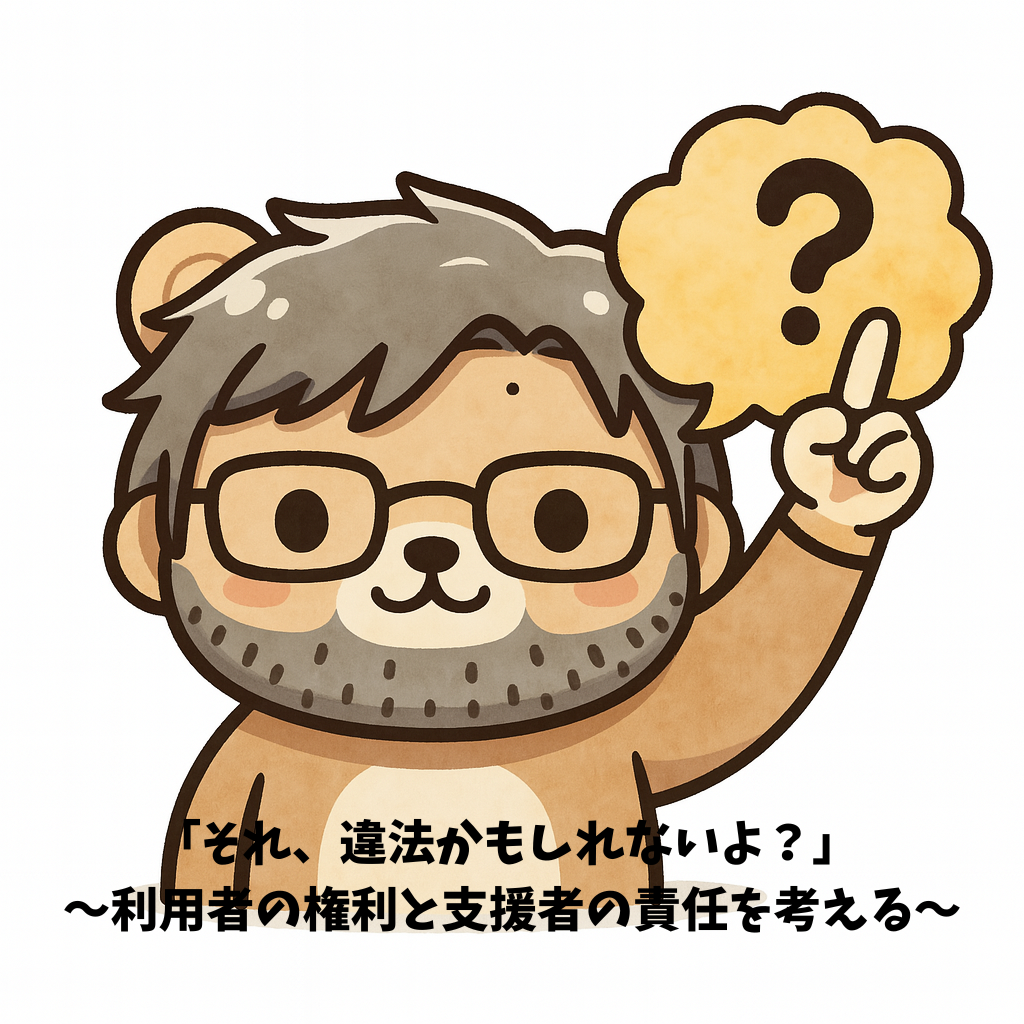
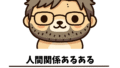

コメント