「帰らなきゃ」「ここは私の家じゃない」
荷物をまとめて玄関に向かう本人の姿に、あなたは戸惑いを感じたことはありませんか?
この“帰宅願望”という行動は、ただの困りごとではなく、
「安心したい」「自分の居場所に戻りたい」という心のメッセージかもしれません。
このページでは、ケア壱と一緒に「帰宅願望」の背景にある気持ちを読み解きながら、
現場で実際に役立った対応のヒントや、少しだけ心がラクになる考え方をお届けします。
◆ 「帰る!」の奥にある“本当の気持ち”
「帰る」「家じゃない」といった言葉の裏には、
以下のような“心の揺れ”が隠れていることがあります。
- 今いる場所がなぜか落ち着かない、不安な感じがする
- 昔住んでいた家の記憶がリアルに思い出されている
- 「家族のためにごはんを作らなきゃ」「迎えに行かなきゃ」という責任感や役割意識
これらは、“家”そのものに帰りたいというより、
「安心できる時間」や「役割を持っていた自分」に戻ろうとする心の旅なのです。
◆ どう対応すればいい?ケア壱のヒント
❏ まずは、否定しない
「ここが家だよ」と説明しても、本人の不安は消えません。
むしろ、気持ちを否定されることで混乱が深まることもあります。
👉 こんな声かけに変えてみましょう:
- 「お迎えの人が少し遅れてるみたいだよ」
- 「今日は泊まるって、お母さんが言ってたよ」
- 「このあと一緒にごはん作ろうか」
ポイントは、“本人の世界”に寄り添う言葉を選ぶこと。
「正す」より「共感する」対応が、落ち着きにつながることもあります。
❏ 環境と心のサポートを両立する
- 居場所を少し変える(テレビのある部屋→静かな部屋など)
- 好きだった家事や役割を軽く再現する(野菜を並べる、洗濯物を畳むなど)
- 家族写真やなじみの物をそばに置く
“心の拠り所”となる環境をそっと用意することで、
本人の不安が落ち着くことがあります。
▶ さらに知りたい方へ【note記事】
「帰宅願望の理解と対応」を、現場視点でさらに深掘りした記事はこちら👇
📘 noteで読む:「帰りたい」を繰り返す母に、私はどう向き合ったか
最後に|ケア壱からあなたへ
帰宅願望は、“不安”や“孤独”のサインでもあります。
その行動の奥にある気持ちを、少しでも受けとめられたら──
きっと介護の空気は、やわらかく変わっていきます。
あなたが誰かの“帰る場所”になれていること。
それこそが、すでに大きなケアです。
💬 ケア壱の名言:「帰りたい」は、役割と安心への帰着点。
🔗 他の認知症ケア記事はこちらから
👉 CRP記事一覧 〜“その人の世界”を理解する 認知症ケアのヒント集〜
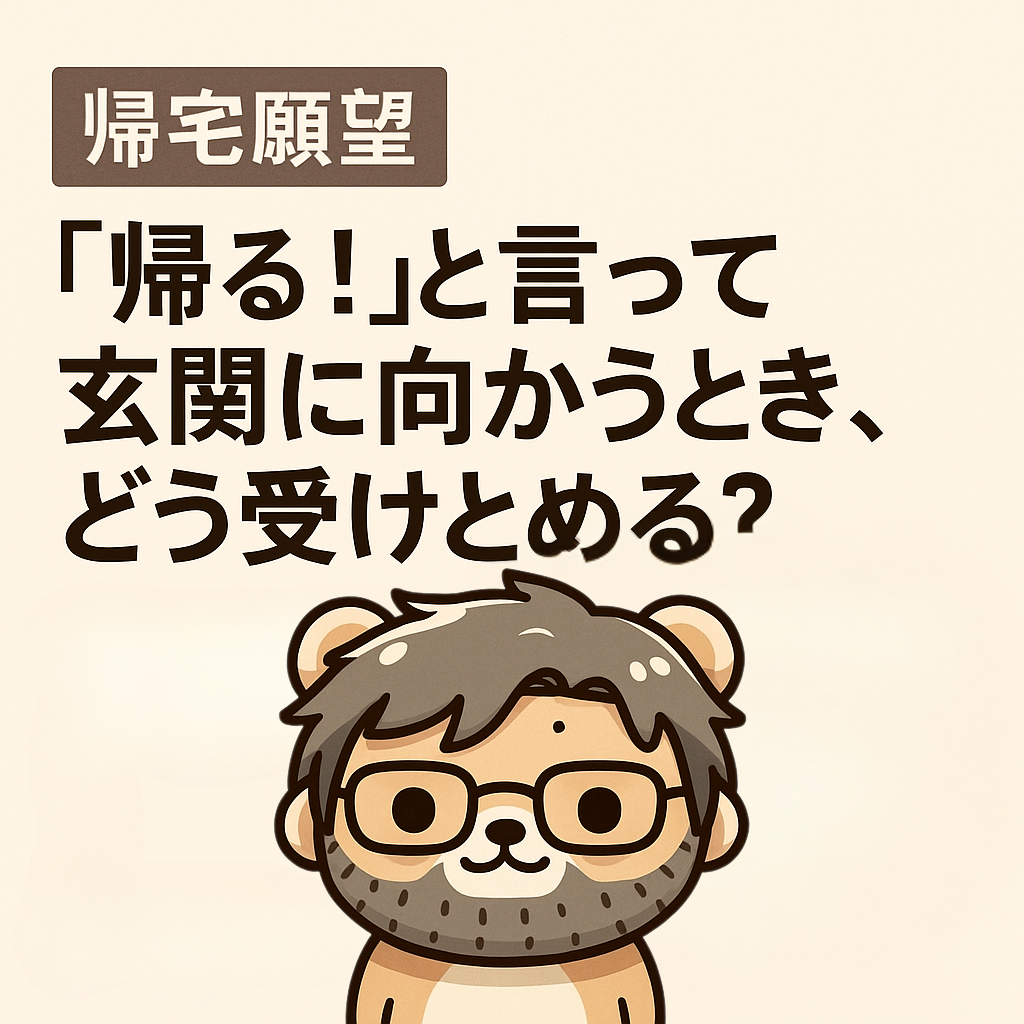
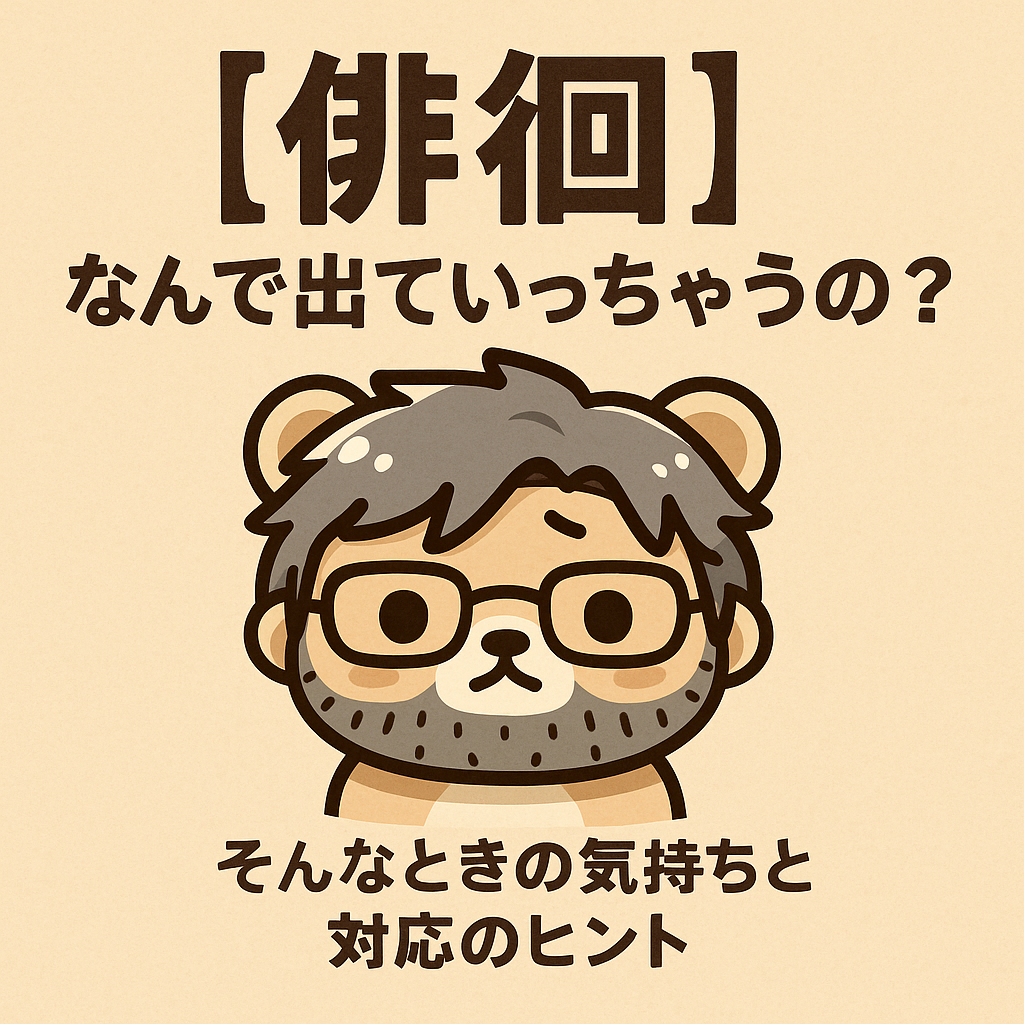

コメント