こんにちは、ケア壱です。
「気づいたら、いなくなっていた」
「夜中に玄関のカギを開けようとしていた」
そんな“徘徊”の場面に、あなたも戸惑ったことがあるかもしれません。
でも――
本人は、ただ歩きたいわけでも、困らせたいわけでもないんです。
◆ 徘徊にも、“理由”がある?
私たちが「徘徊」と呼んでいる行動も、
本人にとっては“意味のある外出”であることが多くあります。
たとえば──
- 「仕事に行かなきゃ」と出ていく
- 「実家が気になる」と昔の記憶をたどる
- 「ここは自分の家じゃない」と感じ、不安から外へ向かう
こうした記憶の混乱や感情の揺れが、行動の背景にあることも少なくありません。
◆ 止めるより、「気持ちを汲む」ことが大切
「出ちゃダメでしょ!」と強く止めても、
本人にはその言葉が届きにくいことがあります。
それは、本人の中では「自分は正しいことをしている」という認識があるから。
▶ たとえば、こんな声かけに変えてみる
- 「仕事に行くの?」→「今日はお休みみたいだよ」
- 「家が違うの?」→「さっきお母さんが“ここで大丈夫”って言ってたよ」
否定しない声かけは、相手の不安や混乱を和らげるきっかけになります。
◆ 無理に止めず、仕組みでサポートする
実際の現場では、“出てしまう前に気づく”仕組み作りもとても大切です。
- センサー付きのライトやチャイムを玄関に設置
- 外出用の靴を隠す or 室内履きにする
- 家の中で落ち着ける“安心の居場所”を作る
環境の工夫+気持ちへの寄り添いが両立すると、
徘徊の頻度が少しずつ減っていくケースもあります。
▶ もっと深く知りたい方は【note】へ
「徘徊って、どう理解したらいい?」
「対応に悩んだとき、どう向き合えばいい?」
「現場でのリアルな声が聞きたい」
そんな方へ、無料で読めるnote記事をご用意しました👇
🔗 【徘徊】何度も出ていこうとする母 どうすればいい?|noteで読む
最後に|ケア壱からのひとこと
“徘徊”という行動の奥には、
その人なりの「理由」や「願い」がきっとあります。
それを知ろうとすること。
少しだけ「見方を変える」こと。
それだけで、あなたのケアがもっと“伝わる”ものになるかもしれません。
💬 ケア壱の名言:「”徘徊”ではなく、安心できる場所探し。」
🔗 他の認知症ケア記事はこちらから
👉 CRP記事一覧 〜“その人の世界”を理解する 認知症ケアのヒント集〜
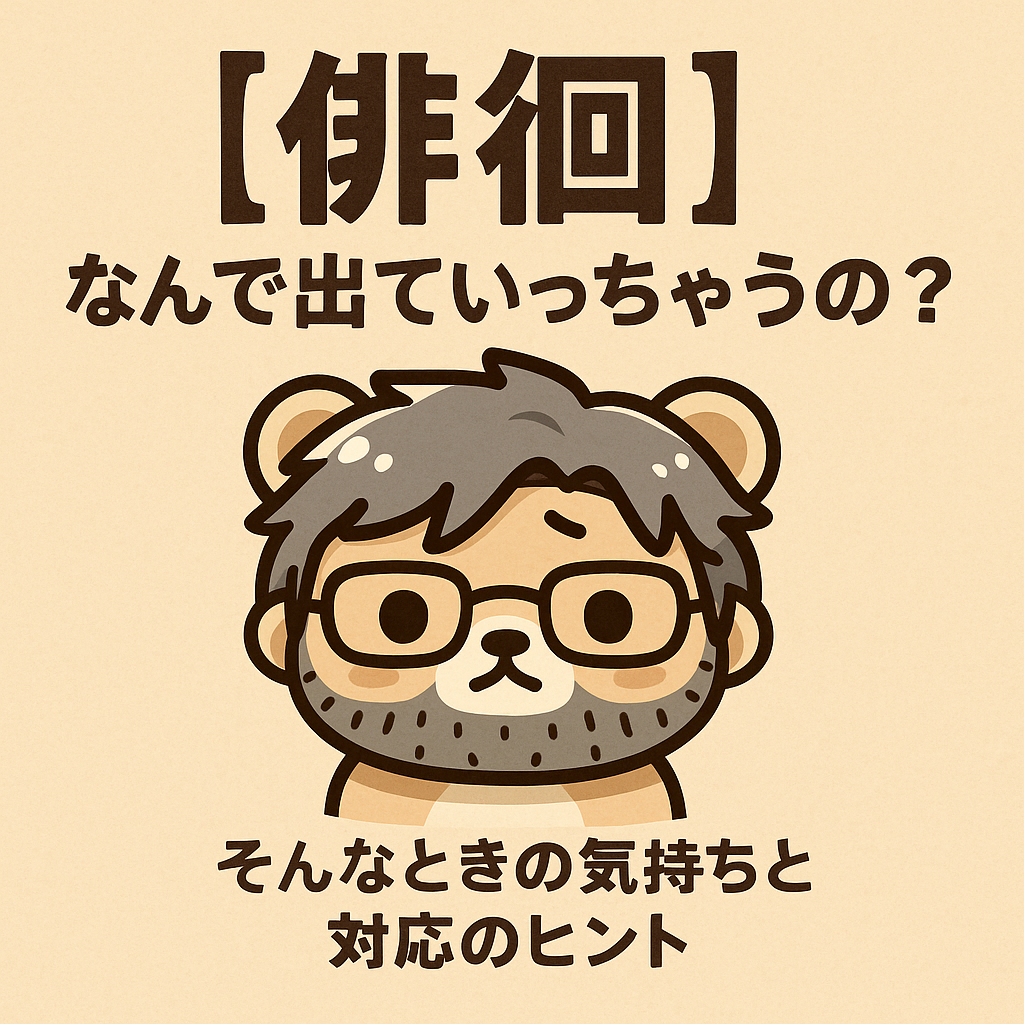

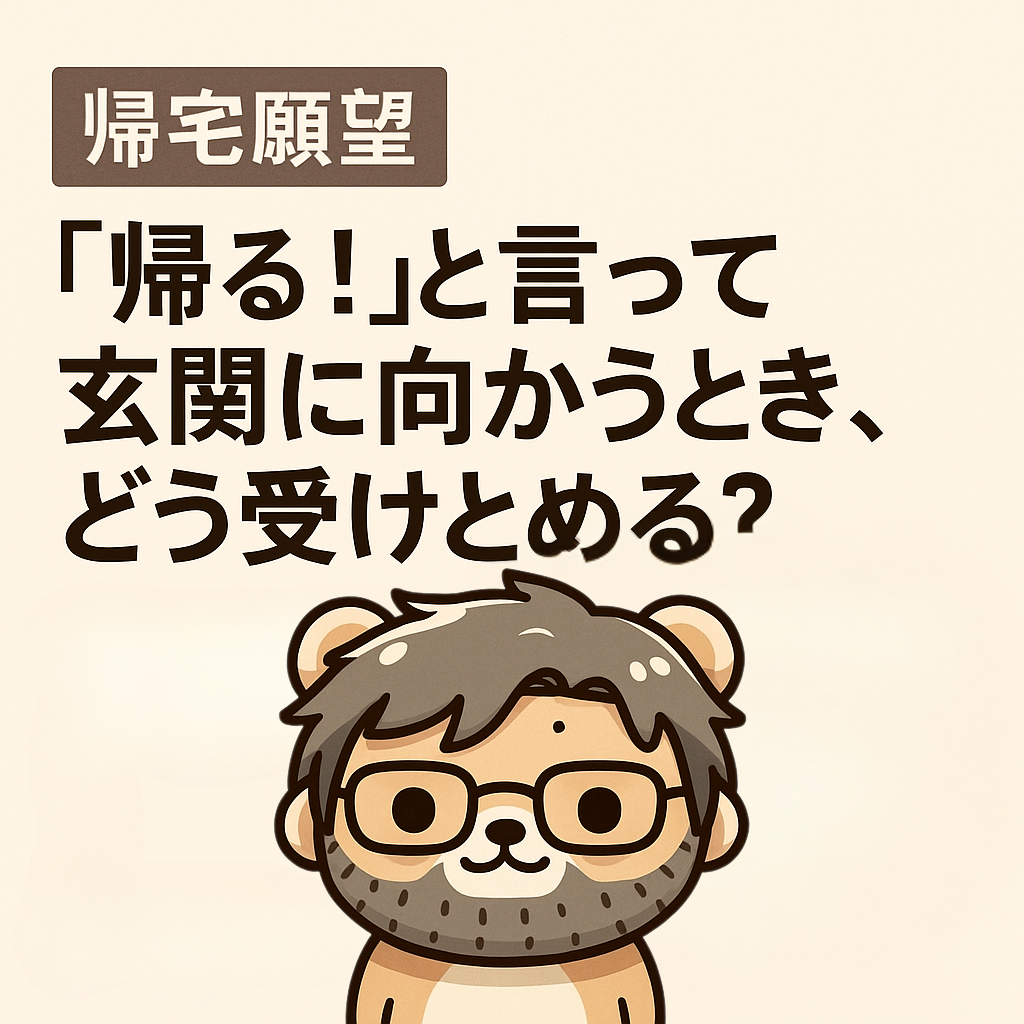
コメント